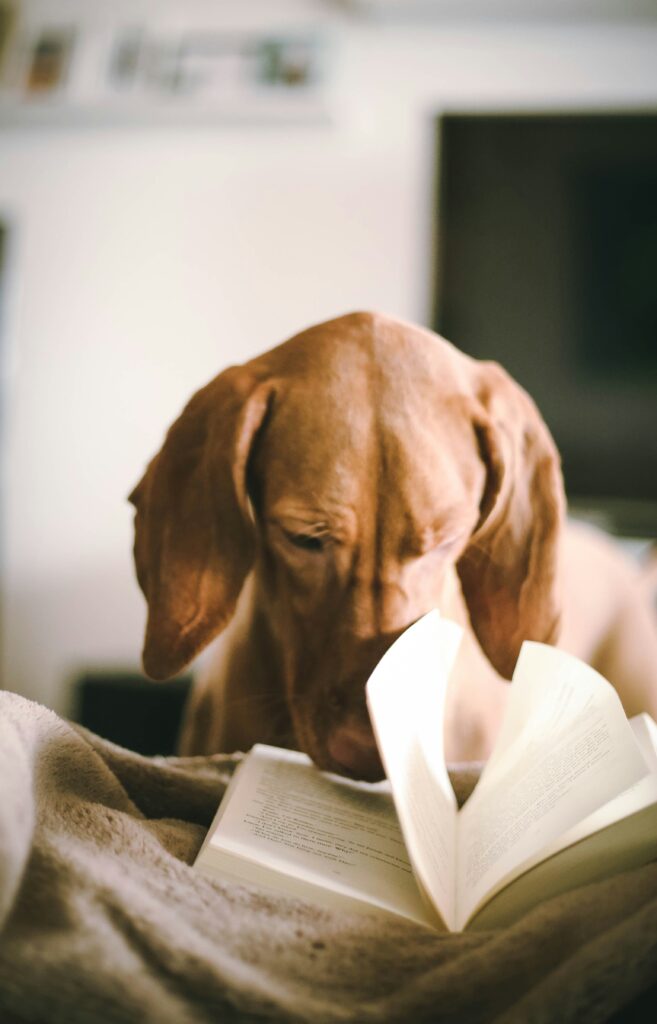
こんにちは。
若者の読書離れが進んでいる、という記事をよく見かけます。
若者、とはいいますが、全年齢的な現象のように思います。
筆者にしても、20年ほど前までは、
月に5~10冊程度は読んでいました。
半分以上は娯楽小説でしたが。
しかし一時期、0冊に落ち込んで、今でも月1~2冊程度です。
個人的な本離れの理由ははっきりしていて、
ブラック企業での一日17時間労働に突入したことです。
さすがに、本を読むより食事と睡眠ですね。
特殊な例はさておき、
現代の本離れもまた、理由はわかりやすいものです。
今回は、本から離れていく人々の姿を見てみましょう。
デジタル媒体への移行で、当然の流れ。本を読まなくなった人々。

今回の毎日新聞の調査を待つまでもなく、
人々の読書離れの傾向は周知の事実です。
~月に1冊も本を読まない人が6割超に上る~
~インターネットで記事などを読む頻度を尋ねる項目では「ほぼ毎日」~
その理由についても、皆さんお察しのとおりですね。
かつて読書に充てられていた時間の多くが、ネット視聴にシフトしたわけです。
今回の調査は16歳以上・3500人程度を対象としています。
およそ60%が月に1冊も読まないと回答し、
そのうち75%がネット上で記事などをほぼ毎日読むと回答。
読書の「舞台」が紙媒体から電子媒体に変わっただけ・・・なのか?

紙の媒体で読んでいた書籍が、時代の流れでデジタル化。
読む場所が変わっただけで、読書の習慣自体はなくなっていない。
そう捉えることもできるかもしれません。
たしかに、筆者の例をとっても、
冒頭のように読書量は激減していますが、
ネットで文章に触れるのは毎日です。
しかし、ネット上で触れる文章は、読書とは別のものであると感じます。
人によっては、正しい意味で
「読書」
としてネット上の文章を読むこともあるでしょう。
しかし多くの人は、何かの調べものや、
興味のある記事、エンタメその他、
読書というよりは情報収集や趣味の読み物、
という使い方をしているのではないでしょうか。
また、その発信内容は?
プロの文筆家が出版社と協力して、
「対価を得て販売する」
という目的のもとに、作り上げられた作品でしょうか?
読者目線で中身を精査・修正・校正を経て送り出されたものでしょうか?
今の時代、非常に手軽に、いち個人が情報の発信ができます。
いま、読んでいる人がいるならば、この文章も、そのひとつです。
ネットの海に漂う言葉の群れの姿はまさに玉石混交で、
誤字・脱字・誤用・文法無視・造語濫用と、
よく言えば自由で縛られないスタイル、
悪く言えば無法地帯です。
言葉は生き物。時代とともに移り変わるもの・・・とはいえ。
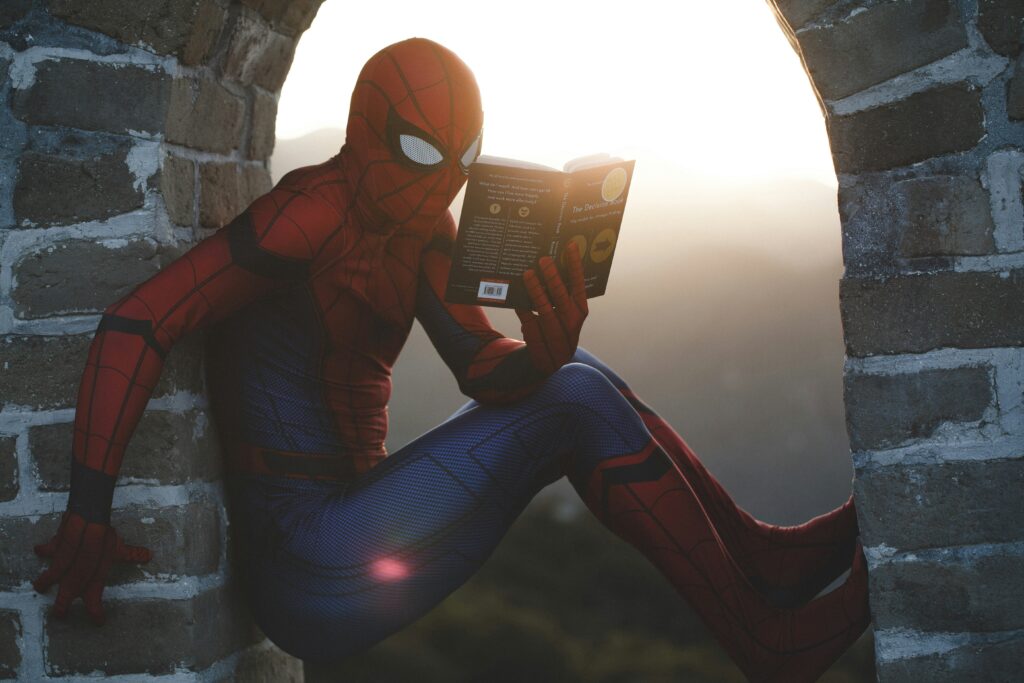
一時期、話題に上った言葉に、
「ら抜き言葉」
というものがあります。
今ではほとんど聞かなくなりました。
→ら抜き言葉について:
文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語施策情報 | 第20期国語審議会 | 新しい時代に応じた国語施策について(審議経過報告) | I 言葉遣いに関すること (bunka.go.jp)
例としては、
「食べることができる」
という意味を表現するのに、
〇食べられる
×食べれる
のように、以前は誤りとされていました。
それが時代の流れとともに、
”ら”を抜いた使用法も、認められるようになり、
今では普通に
「見れる」
「食べれる」
という言葉たちを聞くようになりました。
書籍として完成されたものとそうでないものには、大きな差がある。

ら抜き言葉を例に挙げましたが、
これ以外にも言葉の意味を取り違えて誤用が多発し、
結果、定着するという例があります。

~「失笑する」について、本来とは別の意味で使っていると回答~
~「情報機器で時間を取られるから」~
引用元:「1カ月に1冊も本を読まない」6割超 読書離れ加速…電子書籍利用は増加 「失笑する」を本来とは別の意味での使用が6割以上 文化庁の調査(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
~「間髪を入れず」「悲喜こもごも」「悪運が強い」本来の意味と離れて~
引用元:「もふもふ」使用OKが8割超に!国語に関する世論調査発表「悪運が強い」「悲喜こもごも」は本来の意味が少数派に(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース
言葉というものは一種の生き物のようなもので、
移り変わるのが当然とも言えます。
しかしあまりに安易に
- 意味の拡大解釈
- 別用法の容認
- 誤用に対する過度な寛容
といったゆるい対応を続けると、
短期間に言葉の意味が重複したり、
取り違えの可能性が高まったりと、
大きな危険性を抱えることになります。
ネット利用と、ネット上での読書は別のもの。

すっかり乱文になってしまいましたが、
ネットを読書目的で利用するのであれば、
紙の書籍とデジタル書籍に、大きな差はありません。
(手触りやページをめくる行為など、こだわりたい向きもあるかとは思いますが。)
しかしネット記事などの文章のレベルは、
販売を目的として出版されたものとは完成度が違い、
またそのレベルもさまざまです。
読解力の向上・維持のためには、
媒体はともあれ、きちんと読書をした方がよさそうですね。
それではまた次回。