
こんにちは。
ダークパターンという言葉、
実は筆者も知りませんでした。
しかし、内容はよーく知っています。
どれくらい前から見かけるようになったのか、
思い出せないほど昔から、
実は蔓延しているやり方です。
今回は、誰もが見たことがあるはずの、
感心しない広告の手法について見てみましょう。
ネット広告などで拡大。名前に聞き覚えはなくても知っている?

「イラっ」とする広告に仕込まれていることが多いダークパターンとは?
「ダークパターン」に接触した消費者、サイトの利用を避ける傾向。約4割が「信頼できるアプリやサイトはない」と回答(ネットショップ担当者フォーラム) - Yahoo!ニュース
引用元:Yahoo!ニュース
”消費者を意図しない行動や意思決定に誘導するためにアプリやWebサイトの表示、デザインを設計する「ダークパターン」が近年問題視されている。”
上の引用記事からの抜粋です。
この表現からはピンとこないかもしれませんが、
「押す気もないのにボタンを押してしまった」
「購入・サービス利用をやめたいのに、手間がかかりすぎる」
「NOの選択肢がやたらと小さく手見つけられない」
この手の経験はありませんか?
これらが、今回紹介する「ダークパターン」の代表例です。
しかしこの言葉、まだ一般的とは言えないようで、
最も認知されている20代でも、10%ほどしか知られていないようです。
あまりにも「あるある」な実例たち。実はこれほど身近に。
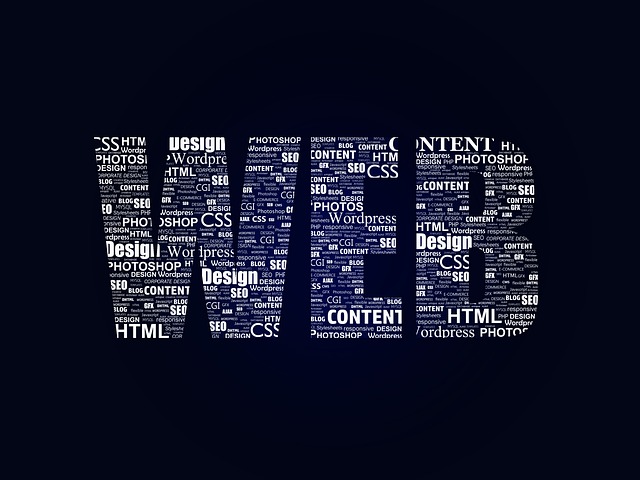
言葉の認知度はイマイチのようですが、
内容はネットユーザーならみんな知っているのではないでしょうか。
拡大する一方の「ダークパターン」、認知2割に対し「押す気はなかったのに広告を押した」が3割で上回る【クロス・マーケティング調べ】(Web担当者Forum) - Yahoo!ニュース
引用元:Yahoo!ニュース
↑↑↑こちらの引用記事に、非常にわかりやすい実例が並んでいます。以下に抜粋しました。
誰もが共感できるはずの実例集。

- ネット通販で、知らないうちに手数料が追加された(されそうになった)
- 1か月無料というので申し込んだら、知らないうちに定期契約に移行していた
- タイムセールのカウントダウンが表示され、つい慌てて購入した(しそうになった)
- 「まもなくセール終了」と表示されたが、実際のセール期間は不明だった
- 高い品の購入ボタンが目立ち、安い商品がわかりにくい
- 選択肢の「はい」「いいえ」が判別しにくく、選びにくい
- ホテルやレストランの予約ページで「現在●名が見ている」を見て、つい予約した(しそうになった)
- ヤラセやサクラのような口コミ・レビューを見かけた
- ネット通販で「在庫僅少」と表示され、つい商品を購入した(しそうになった)
- サービスを解約しようと思っても、解約ページが見つけにくい
- サービス解約の電話がなかなかつながらない
- サービスを解約するために長いアンケートがあり、解約に手間がかかる
- 閲覧に会員登録が必要で、不要だと感じる情報も求められた
- 閲覧のために会員登録をしたら、メルマガの配信も登録された
- 欲しい商品をクリックしたら、調査のためのダミーメニューで買えなかった
- 繰り返しポップアップが表示され、仕方なく「はい」を選択した(しそうになった)
- 初期状態でメルマガを「受け取る」になっていて、いちいち外す必要があった
- 広告が表示され、押す気はないのに誤って押してしまった(押しそうになった)
- 人前で、音が出る広告を間違って押してしまった
- 急に不快な画像や苦手な画像の広告が表示された
~Yahoo!ニュースより抜粋~
https://news.yahoo.co.jp/articles/39cab926533e4e0c20452ecf67b1dfaad96a1cfa
いずれも、ネガティブな実感をともなって思い出される事例です。
多くのユーザーが、これらの経験の後に、
「信用できない」
「もうこのサイトは使いたくない」
と感じるようです。
そうなると広告手法としてマイナスが大きいようにも思えるのですが、
それでも蔓延しているのは、効果があるから、と考えるべきでしょう。
「こうすれば売れる」
への試行錯誤・努力の結果生まれた多くの手法の影の部分が、
これほど世間を蝕んでいると思うと、切なくさえなります。
被害に遭わないために有効な方法は?

これらのステルス的な誘導に気付いて引き返すことができた人は、
「危なかった」
「ヒヤリとした」
で済みますが、誘導されるがままに
「望まない契約」
「意図しない購入」
まで進んでしまった被害もあります。
悪質な広告手法に対する規制の動きはどうでしょうか?
拡大する悪質な手法と被害に対する反応は?

アプリの9割に「ダークパターン」、消費者を欺く画面デザイン…国内の規制は遅れる : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
引用元:読売新聞オンライン
”2022年、EUでは「デジタルサービス法」に合意、
消費者を欺くウェブデザインの設計を禁止”
しています。
日本国内での対応は、残念ながら遅れているようです。
これらの事例は結局のところ、広告の一手法であるにすぎず、
現時点では規制もされず、いわば野放しとなっています。
それでは、身を守る手段はないのでしょうか?
今できる対策は、「知ること」。将来的な規制に期待。

残念ながら、現時点で、
枠組みとしてのダークパターン対策はありません。
世界的なWebのニーズ拡大とユーザビリティ向上の動きに従い、
排除の方向に向かうことが自然ではありますが、
今は自分で認識して回避することぐらいしかできません。
そのために、まずは知っておくことが大切です。
自分自身はもちろんのことですが、
前述のように、世間一般への認知度は高くありません。
用語の認知度の問題で、本質の部分は十分に浸透しているとも言えますが、
単なる「ネットあるある」ではなく、共有すべき社会問題であると
認識を改める時期ではないでしょうか。
それではまた次回。